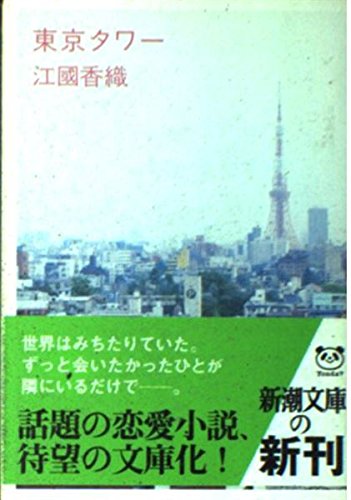面白い本を読めた一ヶ月だった。

面白かった。『ハーモニー』だった。文中で言及されないのが不思議なくらい『ハーモニー』だった。
もっとも現実は『ハーモニー』ではないので大災禍は起きず、未来像の考察にはホモ・エコノミクスを出発点としてこれが文化の発展と自己家畜化(なんだか強烈な語だが専門用語なだけなのだった)をもたらし、エコノミクスの先に人間は進もうとしており云々という感じだった。そこで巨大な政治機構が前提になっていたのだが、政治の仕組みがこの先も "Gewartmonopole" で居られるのだろうか、その前提は大丈夫なのだろうか、という違和感を抱いた。

『すべての男は消耗品である』由来。読むのに時間をかけすぎ、読んだなあ、程度の感想しかない。
生きるというのは制約条件を満たしながらの活動の連続で、その制約条件からエロティシズムが見出せ、時代や集団や社会や文化で制約条件は変わるのでエロティシズムも変わる、サド侯爵はその「制約」からの脱出をやっていこうとしたパイオニアだったのですごい、みたいなもんか。最後のサド云々は本当にこんなこと言っていたかまったく自信が無い。

原題は "TIK-TOK" だけなのになんでこんな凄まじい邦題になったのか、解説まで読んでもよくわからなかった。装丁ありきだったのかしらん。筒井康隆的なノリがずっと続く感じのやつだった。

面白かった。こういう真実がどうとかいう本に近寄っては駄目だと思ってきたのだが、粗筋を読んでみたらしょっぱそうなエピソード集という感を得たので読んだ。『シビリアンの戦争』よろしく現場が一番苦労し民間人も為政者も指導層も現場の苦労というやつを意識しないか出来ないか、そういった気苦労や怒りや嘆きや悲しみを当事者が吐き出す、戦争という現実の記録だった。

泥酔して襲撃に及んだ友人宅の本棚をひっかきまわしていたら出て来、パラパラめくっていたらショートピース(普段これを主にふかしている)がどうこうという断章を目にし、読んでみようと思った。共感性の高い小さくてやわらかく、かつ素朴、そんな感じの観察文の詰め合わせという印象だった。小さい鞄みたいなやつと陽の長さがどうこうみたいなやつが好き。ショートピースのやつは改めて読んでみたら普通だった。

『人間はどこまで家畜か』由来。面白かった。ボトムアップのしたたかさとトップダウンの強権とのうまいバランスをやっていくのがアナキズムという考え方からの現代への応用だ、という感じと読んだ。理屈や道具をあまりにも素直に実世界に適用するな、そういう失敗は歴史でさんざんやられているぞ、というメッセージもあるかしらん。

![ブリキの太鼓 [ディレクターズ・カット版] (字幕版) ブリキの太鼓 [ディレクターズ・カット版] (字幕版)](https://m.media-amazon.com/images/I/41lRSxQ3n0L._SL500_.jpg)















![マッシュ [Blu-ray] マッシュ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51PhfqAsAVL._SL500_.jpg)